
| NPO法人滋賀県ウオーキング協会【イベント報告】 |
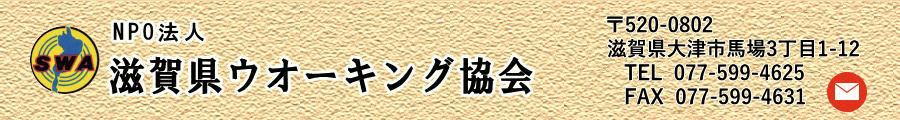 |
| 琵琶湖一周健康ウオーキング2025⑩ 12月14日(日) 曇り後晴れ 126名 近江高島駅~大溝城跡~鵜川四十八体石仏群~白鬚神社~岩除地蔵~北小松駅~北小松水泳場 ~近江舞子駅~比良駅~青柳水泳場~大谷川橋~志賀駅
|
|||||||||||||||
| 琵琶湖一周健康ウオーキング2025⑨ 11月30日(日) 晴れ 144名 近江今津駅~木津交差点~新旭水鳥観察センター~針江浜~源氏浜~安曇川浜園地~横江浜~萩の浜~近江高島駅
|
|||||||||||||||
| 山の辺の道を歩く 11月23日(日) 晴れ 111名 桜井駅~仏教伝来の地~金谷の石仏~大神神社~狭井神社~玄賓庵~桧原神社 ~崇神天皇陵~トレイルセンター~黒塚古墳~柳本駅
|
|||||||||||||||
| 大津なぎさウオーク(牛玉さんの日) 2025年11月18日(火) 曇り・風強し 95名 大津駅~石坐神社~和田神社~膳所城址公園~篠津神社~御殿浜~粟津~瀬田唐橋~石山寺~石山駅
|
|||||||||||||||
| 伊吹の名水を訪ねて 11月16日(日) 晴れ 57名 近江長岡駅~長岡神社の銀杏・ケヤキ~王街道のケヤキ~西山八幡神社~小田分水工~道の駅伊吹の里~三之宮神社 ~ケカチの水~伊吹薬草の里文化センター~泉神社湧水~近江長岡駅
|
|||||||||||||||
| 琵琶湖一周健康ウオーキング2025⑧ 11月9日(日) 雨・風強し 101名 永原駅~大浦園地~二本松水泳場~海津大崎~湖のテラス~今津百瀬川園地~今津浜~今津周遊基地~近江今津駅
|
|||||||||||||||
| 愛知川湖畔林から伊庭の水辺を巡る 10月26日(日) 雨 32名 能登川駅~大濱神社~伊庭城址~伊庭の水辺~金比羅神社~能登川水車~博物館~能登川駅
|
|||||||||||||||
| 大津なぎさウオーク(秋の西近江路を往く) 2025年10月21日(火) 曇り 102名 大津駅~三井寺~尾花川~日本松~際川~唐崎1丁目交差点~唐橋神社~唐崎苑~唐崎駅
|
|||||||||||||||
| 琵琶湖一周健康ウオーキング2025⑦ 10月19日(日) 曇り 135名 木ノ本駅~伊香具神社~賤ヶ岳リフト下広場~賤ヶ岳隧道~藤ヶ崎~塩津神社~道の駅あぢかまの里~岩熊第2トンネル入口 ~大浦口信号左折~JA北びわこ永原支店前信号~永原駅
|
|||||||||||||||
| 大津祭りウオーク 10月12日(日) 曇り 132名 膳所駅~旧東海道~県庁前~天孫神社~大津駅~京町~札の辻~巡行見学~大津駅
|
|||||||||||||||
| ゆっくり巡るヴォーリズ建築 10月5日(日) 曇り後雨 44名 近江八幡駅~ウオーターハウス~小幡駐車場~アンドリューズ記念館~ハイド記念館~ツッカーハウス~ラコリーナ~近江八幡駅
|
|||||||||||||||
| 琵琶湖一周健康ウオーキング2025⑥ 9月21日(日) 晴れ 154名 長浜駅~産直びわみずべの里~姉川大橋~奥琵琶スポーツの森~湖北みづどりステーション ~片山トンネル~赤後寺~木ノ本駅
|
|||||||||||||||
| 大津なぎさウオーク(夏の名残を訪ねて) 2025年9月16日(火) 晴れ 104名 大津駅~(旧東海道)~におの浜~由美浜~近江大橋~琵琶湖漕艇場~唐橋公園~瀬田の唐橋~石山駅
|
|||||||||||||||
| 枝豆収穫ウオーク 9月14日(日) 曇り一時雨 84名 12kmコース マキノ駅~メタセコイア並木~ピックランド~近江中庄駅 6kmコース マキノ駅~湖のテラス~百瀬川~近江中庄駅
|
|||||||||||||||
| KBCウオーク くつの日 京都大会 9月7日(日) 晴れ JR嵯峨野線花園駅~妙心寺~仁和寺~龍安寺~金閣寺~扇町公園~下鴨神社~地下鉄今出川駅
|
|||||||||||||||
| 琵琶湖一周健康ウオーキング2025⑤ 8月31日(日) 晴れ 151名 彦根駅~彦根城~磯南交差点~磯の東屋~朝妻湊跡~世継交差点~近江母の郷~港町交差点~長浜駅
|
|||||||||||||||
| 大津なぎさウオーク(たそがれウオーク) 2025年8月26日(火) 晴れ 80名 大津駅~おまつり広場~なぎさ公園~サンシャインビーチ~膳所城跡公園~松原町~石山駅
|
|||||||||||||||
| 琵琶湖一周健康ウオーキング2025➃ 7月20日(日) 晴れ 137名 能登川駅~葉枝見橋~湖岸緑地柳川公園~草の根広場~多景公園~床堺公園~池州橋~彦根城~彦根駅
|
|||||||||||||||
| 大津なぎさウオーク(琵琶湖の恵みに感謝して) 2025年7月15日(火) 晴れ 188名 大津駅~長等公園~三井寺~疏水~大津港~ミシガン乗船~由美浜~膳所城跡公園~石山駅
|
|||||||||||||||
| 近江妙蓮公園のハスを訪ねて 7月13日(日) 晴れ 100名 守山駅~市民病院前~八代交差点~鳩の森公園~若宮神社~近江妙蓮公園~北川原公園~野洲駅
|
|||||||||||||||
| アジサイの余呉湖一周と北國街道を歩く 6月22日(日) 晴れ 118名 余呉駅~余呉漁港~菊石姫と蛇の目玉石~あじさい園~余呉観光館~意波閉(おはへ)神社~木ノ本地蔵~木ノ本駅
|
|||||||||||||||
| 大津なぎさウオーク(初夏の琵琶湖の眺望を楽しもう) 2025年6月17日(火) 晴れ 106名 大津駅~札の辻~三井寺~丸長~大津城跡~大津港~なぎさ公園~由美浜~膳所駅
|
|||||||||||||||
| 琵琶湖一周健康ウオーキング2025③ 6月15日(日) 曇り時々小雨後雨 135名 近江八幡駅~日牟禮八幡宮~ラ・コリーナ近江八幡~安土城址前~能登川高校前~能登川駅
|
|||||||||||||||
| 保津峡から嵯峨野を巡る 6月8日(日) 曇り後晴れ 151名 保津峡駅~六丁峠~化野念仏寺~二尊院~清凉寺(昼食)~大覚寺~広沢池~嵯峨嵐山駅
|
|||||||||||||||
| 曽根沼公園で落羽松の呼吸根を探そう 6月1日(日) 曇り 75名 稲枝駅~びわこ湖岸緑地・曽根沼公園~荒神山公園~荒神山神社遥拝殿~河瀬駅
|
|||||||||||||||
| 比叡山年輪ウオーク 5月25日(日) 曇り時々雨 56名 ◆往路(行き)Aコース:生源寺~大宮谷林道~横川中堂~玉体杉~峰道広場(11km) Bコース:生源寺~坂本ケーブル駅=延暦寺駅~延暦寺東塔~西塔~峰道広場(6km) ◆復路(帰り)Cコース:峰道広場~延暦寺~大宮谷林道~生源寺(11km) Dコース:峰道広場~(Bコースの逆)~延暦寺駅=坂本ケーブル~生源寺(6km) Eコース:峰道広場解散 *バス等を利用
|
|||||||||||||||
| せっかくウオーク 5月24日(土) 雨 17名 大津駅~関蝉丸神社~長等公園~三井寺~皇子が丘公園~近江神宮~大津京駅
|
|||||||||||||||
| 大津なぎさウオーク(琵琶湖からの春風に吹かれて) 2025年5月20日(火) 晴れ 111名 大津駅~県庁東~なぎさ公園~大津港~疏水~競艇場~びわ湖大津館~二本松~大津京駅
|
|||||||||||||||
| 琵琶湖一周健康ウオーキング2025② 5月18日(日) 晴れ 171名 堅田駅~ピエリ守山港前~中州大橋~めんたいパークびわ湖~家棟川大橋~日野川大橋~岡山園地~高座橋~市立図書館~ 小幡駐車場~中村町信号交差点~桜宮町信号交差点~近江八幡駅
|
|||||||||||||||
| びわ湖長浜ツーデーマーチ 主会場 豊公園 5月11日(日) 余呉湖35km166名・姉川国友20km352名・びわこ北10km419名 937名
|
|||||||||||||||
| びわ湖長浜ツーデーマーチ 主会場 豊公園 5月10日(土) 浅井戦国40km166名・三成ゆかりの地20km398名・びわこ南10km403名 計967名
|
|||||||||||||||
| 水口曳山祭りに往こう 4月20日(日) 晴れ 83名 三雲駅~朝国~泉公民館~柏木小学校~北脇公民館~水口神社~野洲川内貴橋~川田神社~貴生川交差点~貴生川駅
|
|||||||||||||||
| 長浜曳山祭りと北國街道を歩く 4月15日(日) 曇り時々雨後晴れ 56名 田村駅東口駅~田村神社~忍海神社~下坂氏館跡~良疇寺~平方天満宮~豊公園~曳山博物館~長浜駅
|
|||||||||||||||
| 琵琶湖一周健康ウオーキング2025① 4月13日(日) 小雨 137名 大津駅~北國橋~ブランチ大津京~唐崎駅前~穴太神社~生源寺~坂本観光案内所~坂本石積公園 ~おごと温泉観光公園~北雄琴信号~仰木口信号~堅田駅
|
|||||||||||||||
| 大津なぎさウオーク(新しい湖畔の風景と桜の名所を訪ねて) 2025年4月8日(日) 晴れ 122名 大津駅~お祭り広場~なぎさ公園~由美浜~サンシャインビーチ~膳所城址公園~松原~石山駅
|
|||||||||||||||
| 海津大崎・観桜の道 4月6日(日) 曇り時々雨、後晴れ 44名 永原駅~大浦~二本松~海津大崎~マキノ
|
|||||||||||||||
| Copyright©2014- Shiga Walking Association All Rights Reserved |