
| NPO法人滋賀県ウオーキング協会【イベント報告】 |
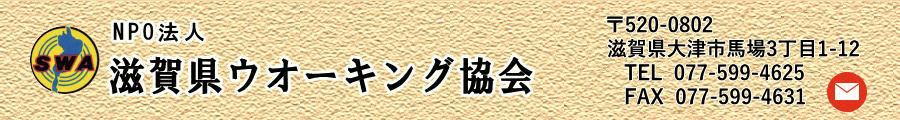 |
| 酒蔵めぐり 2025年3月29日(土) 晴れ 79名 貴生川駅~三雲駅(旧東海道)~弘法杉~北島酒造~甲西駅
|
|||||||||||||||
| 3月23日(日) 晴れ 198名 堅田駅~浮御堂~衣川緑地公園~おごと温泉観光公園~唐崎苑~びわ湖大津館~浜大津~京町~末広町~大津駅
|
|||||||||||||||
| 大津なぎさウオーク(牛玉さんの日) 2025年3月18日(火) 晴れ 112名 大津駅~国道1号~秋葉台~膳所神社~膳所城址公園~瀬田唐橋~螢谷公園~石山寺~石山駅
|
|||||||||||||||
| 安土から近江八幡へ・左義長祭ウオーク 2025年3月16日(日) 雨 31名 安土駅~香庄~西庄~桜宮~中村~小幡駐車場~八幡公園~宮内~日牟禮八幡宮~本町~桜宮~近江八幡駅
|
|||||||||||||||
| 西近江路から東海道 2025年2月24日(月・祝) 雪 74名 大津京駅~二本松~びわ湖大津館~尾花川~三井寺~疏水~北國海道~大津港~旧東海道~膳所駅
|
|||||||||||||||
| 大津なぎさウオーク(牛玉さんの日) 2025年2月18日(火) 曇り後晴れ 94名 大津駅~義仲寺~和田神社~膳所城址公園~旧東海道~瀬田の唐橋~石山寺~石山駅
|
|||||||||||||||
| 琵琶湖一周健康ウオーキング2024⑬ 2月16日(日) 晴れ 157名 近江八幡駅~湖岸白鳥川~湖岸緑地岡山園地~めんたいパークびわ湖~ピエリ守山~琵琶湖大橋~堅田駅
|
|||||||||||||||
| 琵琶湖一周健康ウオーキング2024⑫ 1月26日(日) 晴れ 184名 能登川駅~乙女橋~金刀比羅神社~大中神明宮前~休暇村近江八幡~宮ヶ浜(昼食) ~長命寺港前~近江八幡市立体育館~市立図書館~近江八幡駅
|
|||||||||||||||
| 大津なぎさウオーク(新春の御参詣ウオ-ク) 2025年1月21日(火) 晴れ 140名 大津駅~平野神社~なぎさ公園~大津港~長等商店街~長等神社~三井寺~近江神宮~大津京駅
|
|||||||||||||||
| 初詣ウオーク 2025年1月12日(日) 曇り後晴れ 115名 石山駅~建部大社~瀬田唐橋~石山寺~篠津神社~膳所城址公園~膳所神社~和田神社~石坐神社~膳所駅
|
|||||||||||||||
| 幕末の尊皇攘夷に揺れた城下を往く 2024年12月15日(日) 晴れ 116名 石山駅~瀬田口総門~丹保の宮~安昌寺~膳所神社~遵義堂~膳所城址公園~北口総門~梅林町~大津駅
|
|||||||||||||||
| 大津なぎさウォーク(紅葉の山裾を巡る) 2024年12月10日(火) 晴れ 122名 大津駅~長等公園~三井寺~大津市役所前~丸長~長等商店街~菱屋町商店街~丸屋町商店街~京町~大津京駅
|
|||||||||||||||
| 琵琶湖一周健康ウオーキング2024⑪ 12月8日(日) 曇り後雨 164名 彦根駅~池州橋~多景公園~八坂町南交差点~草の根広場~柳川公園~愛知川橋~小川町交差点~能登川駅
|
|||||||||||||||
| 紅葉の五個荘を訪ねて 2024年11月24日(日) 晴れ 71名 能登川駅~佐生城跡~きぬがさ公園~紅葉公園散策~プラザ三方よし観光案内所~寺前・鯉通り~能登川駅
|
|||||||||||||||
| 大津なぎさウォーク(紅葉の山裾を巡る) 2024年11月19日(火) 曇り後晴れ 111名 大津駅~関蝉丸神社(下社)~長等公園~三井寺~新羅善神堂~皇子が丘公園~近江神宮~大津京駅
|
|||||||||||||||
| 琵琶湖一周健康ウオーキング2024⑩ 11月17日(日) 曇り一時雨後晴れ 174名 長浜駅~港町交差点~近江の館~道の駅「近江母の郷」~朝妻湊跡~松原水泳場~彦根港~金亀公園~彦根駅
|
|||||||||||||||
| 湖南三山を巡る 2024年11月10日(日) 曇り後晴れ 81名 石部駅~雨宮運動公園~常楽寺~長寿寺~下田焼き~甲西駅
|
|||||||||||||||
| 琵琶湖一周健康ウオーキング2024⑨ 11月3日(日) 180名 高月駅~片山トンネル~道の駅「湖北みずどりステーション」~奥びわスポーツの森~産直びわみずべの里~長浜駅
|
|||||||||||||||
| 継体天皇の足跡を訪ねて 2024年10月27日(日) 曇り 52名 近江高島駅~総門~ガリバーホール~慈敬寺(トイレ休憩)~稲荷山古墳見学~天皇橋~えな塚 ~玉泉寺(見学)・長覚寺(昼食・休憩)~田中神社~安産もたれ石~体育館右折~安曇川駅
|
|||||||||||||||
| 琵琶湖一周健康ウオーキング2024⑧ 10月20日(日) 晴れ 161名 近江塩津駅~あぢかまの里~塩津神社~藤ヶ崎~飯浦~賤ヶ岳リフト前(昼食) ~磯野~高月体育館横~北陸自動車道高架下~高月駅
|
||||||||||||||||||||
| 大津なぎさウォーク(古い街並みを歩きます ) 2024年10月15日(火) 曇り一時雨 116名 大津駅~(旧東海道)~石場~膳所駅~膳所神社~膳所城址公園~中ノ庄~杉浦町~別保~石山駅
|
|||||||||||||||
| 大津祭ウオーク 2024年10月13日(日) 晴れ 130名 膳所駅~大津警察署前~浜通り~県庁前~天孫神社~京町~菱屋町~中央通り~大津駅
|
|||||||||||||||
| 野洲豊穣の里を訪ねて 2024年10月6日(日) 晴れ 64名 野洲駅~永原御殿~錦織寺~兵主大社~野洲駅
|
|||||||||||||||
| 琵琶湖一周健康ウオーキング2024⑦ 9月29日(日) 曇り一時少雨 183名 マキノ駅~海津大崎~二本松~大浦公園~大浦口交差点~岩熊第二トンネル ~道の駅「塩津海道あぢかまの里」~近江塩津駅
|
|||||||||||||||
| 大津なぎさウォーク(初秋の近江路を往く) 2024年9月17日(火) 晴れ 82名 大津駅~札の辻~北国海道~皇子山総合運動l公園~二本松~際川~唐崎~唐崎神社~唐崎苑~唐崎駅
|
|||||||||||||||
| 枝豆収穫ウオーク 2024年9月15日(日) 晴れ 99名 マキノ駅~メタセコイア並木~ピックランド~枝豆収穫~近江中庄駅
|
|||||||||||||||
| 長浜六瓢箪めぐりと芭蕉翁句碑を訪ねて 2024年9月8日(日) 晴れ 64名 長浜駅~慶雲館~りょうちゅうじ寺~総持寺~神照寺~神照運動公園(昼食)~舎那院 ~長浜八幡宮~大通寺~知善院~豊国神社~長浜駅
|
|||||||||||||||
| 琵琶湖一周健康ウオーキング2024⑥ 8月25日(日) 快晴 151名 安曇川駅~新旭駅~新旭水鳥観察センター~木津交差点~今津港~今津周遊基地~今津浜~百瀬川橋~マキノ駅
|
|||||||||||||||
| 大津なぎさウォーク(たそがれウオーク) 2024年8月20日(火) 晴れ 74名 大津駅~お祭り広場~なぎさ公園~サンシャインビーチ~膳所城址公園~石山駅
|
|||||||||||||||
| 琵琶湖一周健康ウオーキング2024⑤ 2024年7月21日(日) 快晴 155名 近江舞子駅~北小松駅~白鬚神社~鵜川四十八躰石仏群~乙女ヶ池~勝野交差点~安曇川駅口交差点~安曇川駅
|
|||||||||||||||
| 大津なぎさウォーク(びわ湖の恵みに感謝して) 2024年7月16日(火) 晴れ 138名 大津駅~長等公園~大津港~ミシガン乗船~なぎさ公園~由美浜~膳所城址公園~石山駅
|
|||||||||||||||
| 初夏の花を求めて 2024年7月7日(日) 快晴 58名 守山駅~守山芦刈園~草津水生植物公園みずの森~栗東駅
|
|||||||||||||||
| 特別例会・ウオーキングステーション 琵琶湖なぎさコース 2024年6月27(木) 曇り 42名 膳所駅~(旧東海道)~膳所神社~膳所城址公園~近江大橋~矢橋帰帆島~近江大橋~におの浜~膳所駅
|
|||||||||||||||
| 琵琶湖一周健康ウオーキング2024➃ 2024年6月23日(日) 曇り時々豪雨 145名 堅田駅~小野駅~蓬莱駅~八屋戸浜~志賀駅~比良駅~近江舞子駅
|
|||||||||||||||
| 大津なぎさウォーク(牛玉さんの日) 2024年6月18日(火) 雨後曇り 38名 大津駅~県庁東~(国道1号)~膳所駅~膳所神社~膳所城址公園~瀬田の唐橋~螢谷公園~石山寺~石山駅
|
|||||||||||||||
| 琵琶湖一周健康ウオーキング2024③ 2024年6月9日(日) 曇り時々雨 162名 草津駅~de愛広場(草津川跡地)~ai彩広場(草津川跡地)~烏丸半島~琵琶湖大橋東詰 ~琵琶湖大橋~道の駅「びわ湖大橋米プラザ」~堅田駅
|
|||||||||||||||
| 中山道・武佐宿を歩く 2024年6月2(日) 曇り 68名 安土駅~石寺~奥石神社~武佐宿~近江八幡駅
|
|||||||||||||||
| 琵琶湖一周健康ウオーキング2024② 2024年5月26日(日) 晴れ 231名 瀬田駅~大萱児童公園~大萱6丁目~帰帆南橋~北山田園地~草津川跡地~愛彩広場~de愛広場(草津川跡地)~草津駅
|
|||||||||||||||
| 大津なぎさウォーク(新の山々とびわ湖遠景を眺めて) 2024年5月21日(火) 晴れ 134名 大津駅~朝日ヶ丘~打出中学校横~跨道橋~鶴の里~茶臼山公園~富士見台~園山公園~石山駅
|
|||||||||||||||
| 特別例会・ウオーキングステーション 瀬田川ぐるりさんぽ道 2024年5月16日(木) 晴れ 60名 JR石山駅~螢谷公園~南郷洗堰~瀬田の唐橋~JR石山駅
|
|||||||||||||||
| 第32回びわ湖長浜ツーデーマーチ 2024年5月11(土) 晴れ 伊吹中山道40km・坂田長沢御坊20km・びわこ南10km 計983名 2024年5月12(日) 曇り一時雨 余呉湖35km・姉川国友20km・びわこ北10km 計868名
|
|||||||||||||||
| 源氏物語・宇治十帖を訪ねて 2024年4月21(日) 曇り後小雨 73名 JR宇治駅~橋姫神社~平等院~宇治市観光センター宇治上神社~源氏物語ミュージアム~JR宇治駅
|
|||||||||||||||
| 大津なぎさウォーク 2024年4月16日(火) 曇り後晴れ 102名 大津駅~お祭り広場~なぎさ公園~由美浜~近江大橋~漕艇場~唐橋公園~瀬田の唐橋~石山駅
|
|||||||||||||||
| 琵琶湖一周健康ウオーキング2024① 2024年4月14(日) 晴れ 226名 大津駅~お祭り広場~なぎさ公園・におの浜~サンシャインビーチ~膳所城跡公園 ~瀬田の唐橋~唐橋公園~琵琶湖漕艇場前~大萱六丁目信号~大萱公園~瀬田駅
|
|||||||||||||||
| 第10回海津大崎・観桜の道 2024年4月7(日) 晴れ 91名 マキノ駅~清水の桜~海津~海津大崎~海津~湖のテラス~マキノ駅
|
|||||||||||||||
| 観桜のオランダ堰堤を訪ねて 2024年4月4(木) 晴れ 78名 南草津駅~青山~桐生オランンダ堰堤~小槻神社~草津駅
|
|||||||||||||||
| Copyright©2014- Shiga Walking Association All Rights Reserved |